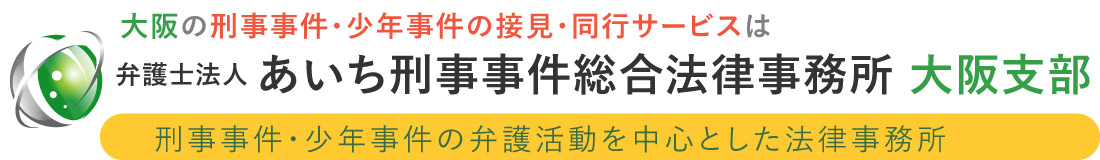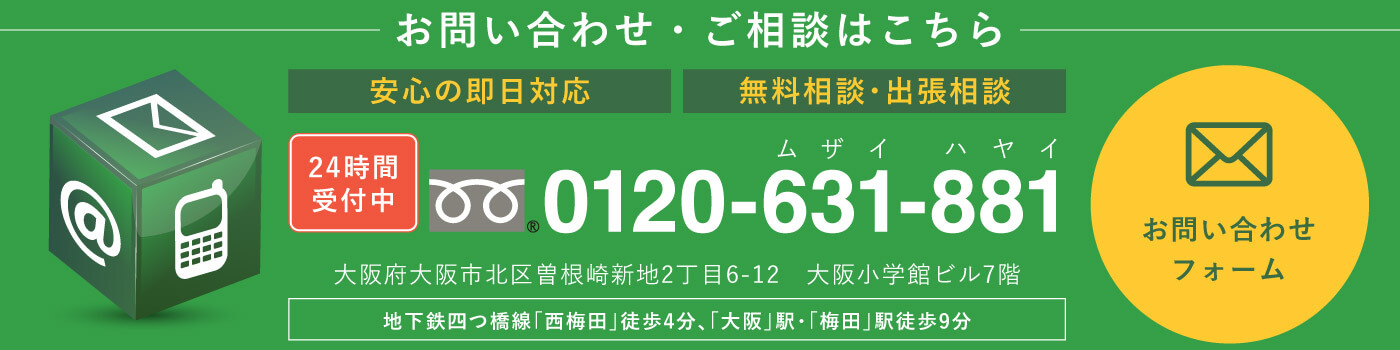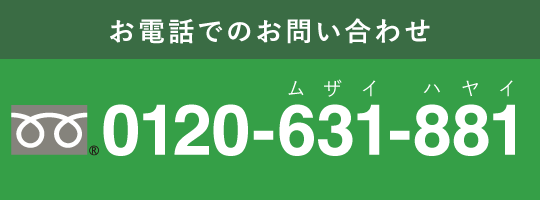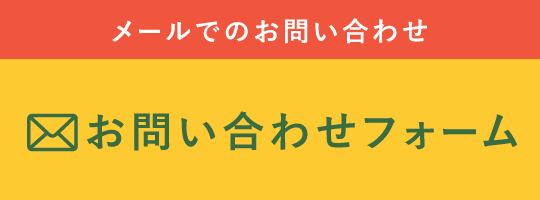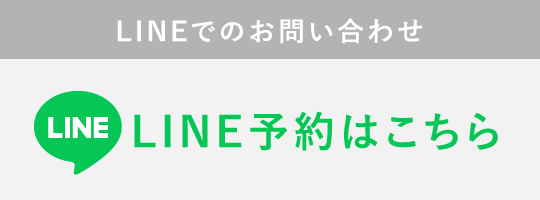Author Archive
学校での体罰暴行事件: 法的視点から見た解説と対処法
学校での体罰や暴行事件は、社会に大きな衝撃を与えます。特に、教育現場で起こる暴行事件は、その影響と法的な対処が注目されがちです。
本記事では、具体的な事例を交えながら、暴行事件がどのように法律で扱われるのか、そして被害者や加害者にどのような法的対処が可能なのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

- 暴行罪とは何か?
- 暴行罪の法的定義と成立要件。
- 具体的事例: 教育現場での体罰暴行事件
- とある私立中学校での事例紹介。(フィクションです。)
- 暴行罪の法定刑と傷害罪の違い
- 両罪の法定刑と成立条件の違い。
- 示談解決の重要性とそのプロセス
- 示談が刑事処罰に与える影響。
- 被害者側の対応策
- 被害者が取るべき法的手続き。
- 加害者の法的責任と対処法
- 加害者の法的責任と弁護士による対処法。
- 予防としての法的教育の重要性
- 学校での法的教育の必要性とその効果。
- 暴行罪とは何か?
暴行罪は、人の身体に対する不法な有形力の行使を指し、刑法第208条により規定されています。この罪が成立するためには、単に相手に触れる行為を超えた、有形力の行使が必要とされます。例えば、教育現場での体罰が暴行罪に該当するか否かは、行われた行為が「有形力の行使」とみなされるかによります。法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、拘留または科料と定められています。
- 具体的事例: 教育現場での体罰暴行事件(*フィクションです)
とある私立中学校で発生した体罰暴行事件では、剣道部の監督である教員が、部活動中に生徒に対して竹刀でのどや脇腹を突くなどの暴行を加えた疑いで逮捕されました。
この行為は、稽古の一環として行われたものの、法律上は「人の身体に対する不法な有形力の行使」とみなされ、暴行罪の適用が検討されました。
警察は、指導日誌やスマートフォンなどを押収し、日常的な体罰が行われていたかどうかを調査しています。
- 暴行罪の法定刑と傷害罪の違い
暴行罪と傷害罪は、ともに人の身体に対する不法行為を処罰の対象としていますが、その成立条件と法定刑には明確な違いがあります。
暴行罪は、人に対して直接的な有形力を行使する行為を指し、その法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
一方、傷害罪は、その行為によって相手に身体的な損害を与えた場合に成立し、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
この違いは、単に力を行使したか(暴行罪)、それによって実際に怪我をさせたか(傷害罪)に基づいています。 具体的には、被害者側の怪我の病院診断書が、警察に提出されているかどうかが、判断の分かれ目になることが多いです。
例えば、教育現場での体罰が暴行にとどまらず、生徒に怪我を負わせた場合、傷害罪の適用が検討されることになります。
このように、暴行罪と傷害罪は、行為の結果によって区別され、それぞれ異なる法的対応が求められます。
- 示談解決の重要性とそのプロセス
暴行傷害事件における示談解決は、刑事処罰の軽減に大きく寄与します。
示談とは、被害者と加害者双方が合意に達し、被害者が加害者を許すことで、訴訟を避ける解決方法です。
このプロセスでは、治療費や慰謝料の支払いが含まれ、被害者の肉体的・精神的な回復を支援します。
また、示談が成立することで、被害届の取り下げや病院診断書の提出を阻止し、加害者に対する刑事処罰の軽減が期待できます。
刑事事件に強い弁護士に依頼し、示談交渉を進めることは、加害者にとっても被害者にとっても、最善の解決策となる場合が多いです。
教育現場での体罰暴行事件では、特に未成年が被害者となるケースが多く、その保護者との示談交渉が重要となります。
- 被害者側の対応策
被害者やその保護者は、暴行事件に遭遇した際、適切な対応を取ることが重要です。
まず、事件の証拠を確保するため、医療機関での診断を受け、診断書を取得することが必要です。
この診断書は、後の法的手続きにおいて、被害の程度を証明する重要な書類となります。
次に、警察に被害届を提出し、事件の正式な記録を残すことが、加害者に対する法的措置を講じる上での第一歩となります。
また、弁護士に相談することで、被害者側の権利を守り、適切な示談交渉や法的措置を進めることができます。
特に、未成年者が被害者の場合、その心のケアも重要であり、専門家によるサポートを受けることも考慮するべきです。
被害者側の対応は、迅速かつ適切に行うことで、その後の法的手続きや心理的回復に大きく影響します。
- 加害者の法的責任と対処法
加害者が直面する法的責任は、その行為が暴行罪や傷害罪に該当するかによって大きく異なります。
暴行罪は、人の身体に対する不法な有形力の行使を指し、傷害罪はその結果として相手に怪我を負わせた場合に適用されます。
加害者は、刑事訴訟において重い刑罰に直面する可能性がありますが、示談による解決が可能な場合もあります。
この場合、弁護士を通じて被害者側との示談交渉を行い、治療費や慰謝料の支払い、被害者の許しを得ることが、刑事処罰の軽減につながります。
加害者は、法的責任を認識し、適切な法的対処を行うことが重要です。
刑事事件に強い弁護士に相談し、早期の段階で対応策を講じることが、最終的な刑罰を軽減するために不可欠です。
- 予防としての法的教育の重要性
教育現場での暴行事件を未然に防ぐためには、法的教育の強化が不可欠です。
生徒だけでなく、教員に対しても、暴行罪や傷害罪などの法律知識を含めた綿密な教育を行うことが重要となります。
このような教育を通じて、教育関係者は自身の行動が法律によってどのように規制されているかを理解し、不適切な行為を自制することが期待されます。
また、生徒に対しても、自分や他人が不法な行為の被害者または加害者になった場合の法的な意味や影響を教えることで、法の尊重と正しい行動の促進を図ることができます。
予防教育は、単に法律の条文を教えるだけでなく、実生活での適用例や判断基準を含めた実践的な内容であるべきです。
この取り組みにより、教育現場での暴行事件の発生を減少させ、より安全で健全な学習環境の実現に寄与することが期待されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大阪支部では、大阪府内のみならず近隣の府県で刑事事件でお困りの方からの法律相談を初回無料で受け付けております。
フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。
2023年司法試験予備試験受験生アルバイト求人募集
2023年司法試験予備試験受験生アルバイト求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2023年の司法試験又は予備試験受験生の方を対象に、全国12都市にある各法律事務所で事務アルバイトを求人募集します。試験の合否は問いません。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイトについて
司法試験に最終合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要な要因になります。長い勉強生活の中で、快適な勉強環境が確保できなくなる時期やモチベーションが低下して勉強に身が入りづらい時期もあるかもしれません。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。試験勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生は是非ご応募下さい。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に注力し、著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
・事務アルバイト:時給1,300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1,300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1,000?1,300円となります。
【勤務地】
大阪支部 大阪駅、梅田駅から徒歩9分
弁護士法事人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、最寄りの西梅田駅から徒歩5分、大阪・梅田駅からも徒歩9分程度という各方面からの通勤アクセスが非常に良い場所にあり、隣接する京都支部、神戸支部と連携して、関西圏全域の法律相談や初回接見に対応しています。
取り扱う事件は、大阪地方検察庁や大阪地方裁判所が管轄する大阪市内・大阪府内の刑事事件・少年事件を中心に兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県といった関西全域にも及ぶ広範囲の刑事事件・少年事件を取り扱うことになるため、事件種類も多様であり、刑事事件・少年事件専門の弁護士による刑事弁護活動や付添人活動を間近に見ることができます。
勉強しているだけではわからない刑事弁護活動の実務を間近で見ることができますので、試験突破に向けた勉強のモチベーションにもつながります。
法律事務所の仕事や雰囲気を通じて社会人経験を積める環境でのアルバイトは、法曹界を目指す若い世代の方々にとって、とても有意義な時間となることは間違いありません。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※ご希望に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・事務アルバイト
事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【勤務環境】
・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
司法試験・予備試験受験生アルバイト応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の予備試験受験生向けアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

大麻リキッドを押収された 逮捕をおそれて帰宅しないと…
大麻リキッドを押収された方が、逮捕をおそれて帰宅しなかった場合のリスクについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
無職のAさんは、数日前に大阪ミナミのクラブで知り合った外国人から大麻成分の含有したリキッド(大麻リキッド)を購入しました。
その後Aさんは、大阪府南警察署の管内で、バイクを運転中に交通事故を起こしてしまい、事故処理の際にカバンに入れて隠し持っていた、この大麻リキッドが警察官に見つかり、押収されてしまったのです。
Aさんは、警察官に対して「合法なリキッドだ。」と説明しましたが、警察官からは「これから大麻かどうか鑑定する。鑑定結果によっては逮捕するかもしれない。」と言われ、その日は帰宅することができました。
今後逮捕されることをおそれたAさんは、自宅に戻らず逃亡生活を始めました。
(フィクションです。)
大麻所持罪(大麻取締法違反)
大麻を規制している大麻取締法では、大麻の栽培、輸入・輸出、所持、譲渡、譲受等が禁止しており、違反した場合の罰則が規定されています。
大麻取締法では、大麻を不法に所持することを禁止しており、これに違反した場合は、非営利目的で「5年以下の懲役」の罰則が設けられています。ちなみに、営利目的で所持していた場合には「7年以下の懲役情状によって200万円の罰金を併科」と罰則が厳罰化されています。
かつては大麻所持事件といえば乾燥大麻が大半を占めていましたが、最近はリキッドタイプのものが多く出回っています。
大麻リキッドは、様々な成分が混じっているため鑑定に時間がかかる場合があり、最近は、押収現場での簡易鑑定は行っていないようです。
そのため大麻所持容疑で警察に逮捕される場合は、科学捜査研究所で鑑定がなされて、その結果によって、後日通常逮捕されることになります。
逮捕から逃れるために逃走すると
Aさんのように、警察の逮捕から逃れるために逃走すると、どうなってしまうのでしょうか?
逮捕から逃れるために逃走している事実が発覚すれば、警察は逮捕状を取得して行方を捜査するでしょうし、場合によって指名手配されて顔写真等が世間に公開される可能性もあり得ます。
またいつまで逃げれば逮捕されるリスクがなくなるのかと考えると、それは、時効が成立するまで逃げ切るしかありません。
大麻所持罪(非営利目的)の公訴時効は「5年」ですので、逃走によって逮捕を完全に免れるには、事件が発覚した日から5年間もの長期にわたって逃げ続ける必要があります。
友人や、知人の援助を受けながら逃走した場合は、その友人や知人が犯人隠避罪や、犯人蔵匿罪などといった罪名で逮捕される可能性もあるので注意しなければならないでしょう。
まずは弁護士に相談を
大麻所持事件等の薬物事件でお悩みの方は、まずは刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、こういった刑事事件に関する弁護士のご相談を初回無料で承っておりますので、無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

【謹賀新年】お正月の刑事事件に即日対応している弁護士
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

さて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、お正月に急遽弁護士が必要になった方からの、無料法律相談や初回接見サービスに即日対応している法律事務所です。
本日1月1日から1月3日までのお正月休み中でも
フリーダイヤル 0120-631-881
は、24時間受付ておりますので、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関する法律相談を初回無料で承っております。
お正月休みの間に弁護士に相談しておきたい事件がございましたらお気軽にフリーダイヤルまでお電話ください。
初回接見サービス
大阪府内の警察署また、近隣府県の警察にご家族等が逮捕されてしまった方は、警察署まで弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、お正月も刑事事件専門の弁護士が即日対応しておりますので、フリーダイヤルにて初回接見サービスを申込みください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、2024年今年一年が、皆様にとって良いお年であることを願っております。
空き家に残飯投げ捨て 威力業務妨害容疑で逮捕
隣の空き家に残飯投げ捨てるなど迷惑行為繰り返していた男が威力業務妨害容疑で逮捕された事件を参考に、威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件(12月25日配信のYTV記事を引用)
隣の空き家にごみを投げ捨てるなどの迷惑行為を繰り返していた男が、威力業務妨害の疑いで警察に逮捕されました。
被害を受けていた空き家を管理する不動産会社が、空き家に設置した防犯カメラに、逮捕された男が残飯などのごみを投げ入れたり、門を破壊したりする様子が記録されていて、不動産会社は設置した看板が壊されたとして警察に被害届を提出していたようです。
威力業務妨害
逮捕容疑となった威力業務妨害罪は刑法第234条に規定されている犯罪行為で、違反すると「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害した場合に成立するので、今回の事件で警察は、ゴミを投げ入れたり、門を壊す行為は、威力業務妨害罪における「威力」に該当し、それによって空き家を管理する不動産会社の業務を妨害したと捉えて、威力業務妨害罪を適用したのでしょう。
他の犯罪に抵触する可能性もある
報道によりますと、逮捕された男は、空き家にゴミを投げ入れたり、空き家の門扉を破壊しているようです。
ゴミを投げ入れる行為は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に抵触する可能性があります。
また、門扉を破壊する行為は門扉の形状にもよりますが、器物損壊罪や、場合によって建造物損壊罪に抵触する可能性があります。
逮捕容疑である威力業務妨害罪の他にこういった別の犯罪が成立するかどうかは、今後の捜査次第となるでしょうが、別途成立する場合は、より厳しい刑罰が科せられ可能性があるので注意が必要です。
まずは弁護士に相談
ご家族等が、威力業務妨害罪で警察に逮捕されてしまった場合は、警察署に弁護士を派遣することからはじめましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士を警察署に派遣する 初回接見サービス を提供しております。
このサービスは電話で予約いただくことができ、ご予約いただいたその日のうちに対応ができる非常に便利なサービスです。

同僚と喧嘩 正当防衛or相被疑傷害事件
同僚と殴り合いの喧嘩をした場合、正当防衛が成立するのか、それとも相被疑傷害事件となるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
大阪府貝塚市のビル解体現場で働いているAさんは、解体工事中の手順を巡って、同僚と口論になりました。
その際に同僚から胸倉を掴まれたことが発端で、お互いにつかみ合いになり、最終的にはお互いに殴り合う喧嘩に発展してし、二人とも顔面から出血する傷害を負ったのです。
Aさんは、相手が先に手を出したのだから、自分の行為は正当防衛だと思い込み、大阪府貝塚警察署に、喧嘩した同僚を傷害罪で訴えたのですが、その際に、警察官からは「相被疑傷害事件ですよ。あなたは被害者でもあり、加害者でもあります。」と言われました。
(フィクションです)
正当防衛
まず正当防衛について解説します。
正当防衛は、刑法第36条に規定されている法律で、急迫不正な侵害に対し、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為が正当防衛です。
正当防衛でいう「脅迫不正の侵害」とは、法益の侵害が現に存在しているか、又は直前に迫っていることをいいます。
したがって、過去の侵害や、未来の侵害に対しての反撃行為は、正当防衛とはいえません。
ただし、威力のある防犯装置を設置する場合、同装置が、現に発生した不正な侵害に対して相当な効果を発揮するものであれば、未来の侵害に対して備えたものでも正当防衛が認められる場合があります。
次に、「不正」とは、違法であればよく、有責であることまで必要ありません。
したがって、刑事責任能力のない者による侵害行為に対しても、正当防衛が成立します。
また「侵害」とは、生命・身体に危険を生じさせる違法な行為を意味し、故意・過失や、作為・不作為を問いませんが、積極的な侵害行為でなければなりません。
続いて「やむを得ずにした行為」とは、急迫不正の侵害に対する防衛行為が、自己又は他人の権利を守るために必要最小限度でなければなりません。
ここでいう「必要最小限度」とは、防衛行為により生じた結果ではなく、その防衛行為が必要最小限度であることを意味するので、防衛行為によって相手が重傷を負った場合でも、その防衛行為が必要最小限度であると認められれば正当防衛が成立します。
相被疑傷害事件
今回のような殴り合いの喧嘩をしてお互いに傷害を負った場合は相被疑傷害事件となります。
Aさんのように相被疑の傷害事件に巻き込まれた場合、まず大切なのは、事件後速やかに、病院で診察を受け医師の診断書を得ることです。
よく相被疑の傷害事件に巻き込まれた方で、相手が被害届を出したら、こちらも被害届を出すという方がおられますが、その様な場合でも、診断書を得ないまでも、少なくとも医師の診察を受けておくことをお勧めします。
もし事件からしばらく経過して相手が警察に被害届を提出した場合、それから医師の診察を受けても、相手からの暴行で傷害を負ったかどうかの因果関係の立証が難しくなるばかりか、怪我が完治して診断書を得れない場合があるからです。
その場合、自身の行為は傷害罪の適用を受けますが、相手は、傷害罪よりも軽い暴行罪までしか適用されない可能性があり、その後の刑事罰に差異が生じてしまいます。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、相被疑の傷害事件ですと、怪我の程度にもよりますが、ほとんどの事件が、不起訴処分か、略式罰金刑となります。
暴力事件の弁護活動を得意とする弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、相被疑傷害事件などの暴力事件の弁護活動を得意とする法律事務所です。
このような事件でお困りの方からの無料法律相談や、このような事件で逮捕された方への初回接見サービスを、年中無休で承っております。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

レンタカーを乗り逃げ 事故を起こして横領罪で逮捕
レンタカーを契約期限過ぎても返却せずに使用を続けたとして横領罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
大阪府茨木市に住む無職のAさんは、約2カ月前に市内のレンタカー会社で3日間の契約で車を借りましたが、契約期間を経過してもAさんは、レンタカーを返却せず使用し続け、レンタカー会社への連絡もしませんでした。
そんな中、そのレンタカーを運転中に交通事故を起こしたAさんは、事故処理のために臨場した大阪府茨木警察署の警察官からレンタカー会社から被害届が出されていることを告げられて、Aさんは横領罪で逮捕されてしまいました。(事件は実話を基にしたフィクション。)
横領罪
横領罪とは、自己の占有する他人の物を横領することによって成立する犯罪です。
横領罪が成立するには「本人排除の意思」が必要となります。
本人排除の意思とは、その物の持ち主の意思と関係なく、勝手にその物を処分する意志のことで、窃盗罪等の財産犯が成立するのに必要とされる「不法領得の意思」と同じようなものです。
※不法領得の意思とは「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用処分する意思」です。
横領罪に未遂はない
横領罪に未遂の規定はありません。
未遂とは、犯罪に着手しながらも成しえなかった場合をいいますが、横領罪の場合、既に自分の手元にある財物について、上記した本人排除の意思が生じると同時に既遂に達するとされているからです。
仮に、「このまま返却せずに乗り逃げしてやろう。」という意志のもとでレンタカーの契約をしていた場合は、詐欺罪が成立するでしょう。
ただ、その意思は犯人のみぞ知り得る場合がほとんどなので、今回のようなレンタカーの乗り逃げについては、横領罪が適用されるでしょう。
横領事件で逮捕されたら
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、ご家族が警察に逮捕された方から 初回接見 を承っております。
この初回接見サービスは、電話でご予約が完了する非常に便利なサービスで、ご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することもできますので、詳しくは
フリーダイヤル 0120-631-881
に、お問い合わせください。

19歳の男を逮捕 被害者の高齢男性が死亡
高齢男性に対して暴行したとして19歳の男が傷害罪で警察に逮捕されましたが、被害を受けた高齢男性はその後死亡しました。
本日のコラムでは、この事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が解説します。
事件報道(11月25日配信のテレ朝ニュースの引用)
堺市中区の集合住宅において、高齢の男性に暴行を加えて怪我をさせたして19歳の男が傷害罪で逮捕されました。
犯行後、逮捕された男は自ら119番通報しており、その際に「高齢の男性が文句を言ってきて言い合いになった」と話していたようです。
被害を受けた高齢男性は、搬送先の病院で死亡しています。
なぜ傷害罪?
報道によりますと、19歳の男の逮捕罪名は「傷害罪」です。
被害者が亡くなっているのになぜ傷害罪なの?と疑問に思う方もいるかと思いますが、報道されているのは逮捕罪名、すなわち逮捕時に適用された罪名です。
おそらく警察官が現場にかけつけ、容疑者の男を逮捕する際は、まだ被害男性が生存していたので、傷害罪が適用されたものと思われます。
そしてその後、死亡が確認されると、検察庁に送致される段階で「傷害致死罪」に適用罪名が変更されるでしょう。
傷害罪と傷害致死罪の違い
人に怪我を負わせると傷害罪となります。
今回のように、暴行によって人に傷害を負わせる傷害罪については、傷害の故意までは必要とされず、暴行の故意があれば傷害罪が成立します。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
そして、故意の暴行行為によって傷害を負った被害者が死亡してしまうと「傷害致死罪」となります。
傷害致死罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」と厳しいもので、法律的には起訴されて有罪が確定したとしても、執行猶予を獲得することができますが、結果の重大性から執行猶予の獲得は非常に難しいのが現状です。
今後について
今回逮捕されたのは19歳の男です。
通常であれば少年法による手続きが進む可能性が高いのですが、傷害致死罪は、原則として家庭裁判所から検察庁に逆送されるので、検察庁に逆送後は、起訴されて成人と同じ法廷における刑事裁判を受けることになる可能性が非常に高いです。
また刑事裁判は、一般人が審議に参加する裁判員裁判で行われるので、弁護人は、通常の刑事裁判よりも高度な専門知識と豊富な経験のある専門弁護士を選任しておくことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
刑事弁護活動の専門知識と経験豊富な弁護士が揃っていますので、傷害罪や傷害致死罪に関する 法律相談 をご希望の方は是非、ご相談ください。

放課後デイ施設で暴行 運営会社代表らを逮捕
放課後デイの利用者に対して殴るなどの暴行を加えたとして、施設の運営会社の代表等が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(11月21日配信の時事通信社記事を引用)
大阪府吹田市の放課後デイサービスにおいて、施設の利用者の少年が、施設を運営する会社の代表らに暴行されていました。
逮捕されたのは運営会社の代表や、施設の従業員など3人で、3人は、施設内で重度の知的障害がある当時中学3年の少年の顔をバランスボールで殴打したり、頭を壁に打ちつけたりするなどの暴行を加えた疑いがもたれています。
事件の発覚
報道によりますと、今回の事件が発覚したのは、全く別の事件(施設利用者が行方不明になり、その後死亡しているのが発見された事件)の捜査で大阪府警捜査一課が、施設内の防犯カメラ映像を確認したところ、本暴行事件が発覚したようです。
今回の事件の被害者は知的障害があるようなので、こういったかたちで発覚しなければ事件の立証どころか、発覚すらしなかった可能性が高いでしょう。
放課後デイ施設での事件
障害のある子供達を預かり生活の面倒をみる放課後デイ施設は、ここ数年で非常に増加しており、様々な問題点が浮きぼりになって世間を騒がせていますが、今回のような刑事事件の舞台となることも少なくないようです。
今回の事件は暴行事件ですが、施設の利用者が、施設の従業員等による性犯罪の被害にあう事もあります。
こういった立場を利用しての犯行は、非常に悪質性が高く、厳しい刑事罰が科せられる可能性が高く、逮捕される可能性も非常に高いでしょう。
暴行事件で逮捕されると…
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は科料」とそれほど厳しいものではなく、通常の暴行事件の場合は逮捕のリスクもそれほどありませんが、この手の事件は逮捕される可能性が高く、逮捕後に勾留が決定するのも間違いないでしょう。
そのため弁護士は、まずは早期釈放を求める活動を行い、その上で、被害者の親御様等と示談して不起訴を求めることになります。##
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
暴行罪のような粗暴犯事件に関する ご相談 や 初回接見サービス については、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

酒に酔った客を路上に放置 保護責任者遺棄致死罪で逮捕
バーの経営者が酒に酔った客を路上に放置したとして、保護責任者遺棄致死罪で、大阪府南警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
Aさんは、大阪ミナミの歓楽街にあるビルの一室を借りてバーを経営しています。
2週間ほど前に、一人で来店していた常連客がお店の中で酔い潰れてしまい、閉店時間になっても寝込んだままだったので、Aさんは閉店してお店を出る際に、この常連客を抱えて店外に出し、ビルの階段に放置して帰宅したのです。
そうしたところ、翌日、ビルの清掃業者が亡くなっているこの常連客を発見したのです。
すぐにAさんは大阪府南警察署に呼び出されて事情聴取を受けたのですが、それからしばらくして保護責任者遺棄致死罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
保護責任者遺棄致死罪
幼児や高齢者、身体障害者、病人を保護する責任がある者が、放置したり、生存に必要な保護をしなかったりして、要保護者を死亡させると、保護責任者遺棄致死罪となる可能性があります。
保護責任者遺棄致死罪で客体となる要保護者とは、老年者、幼年者、身体障害者又は病者です。
ここでいう「病者」とは、刑法第217条に規定されている「遺棄罪」でいうところの疾病のために扶助を必要とする者と同じ意味です。
病気や傷害等により、肉体的、精神的に疾患のあることを意味し、その原因のいかん、治癒の可能性の有無、疾病期間の長短は問われません。
薬物等の影響や、泥酔ににより意識を失っている者もこれに含まれます。
ちなみに、扶助を必要とする者とは、他人の助けがなければ日常生活を営むための動作ができない者で、生活資力を自給し得るかどうかは問われません。
保護責任者遺棄致死罪の主体は?
保護責任者遺棄致死罪で主体となるのは、上記客体を保護する責任のある者に限られます。保護責任は、法令の規定、契約、慣習、事務管理、条理によって発生する法律上のものでなければなりません。
幼児の保護者や、老人の介護者は当然のこと、病人を看護する看護師や、幼児の面倒をみるベビーシッターも保護責任者遺棄致死罪の主体となるでしょう。
Aさんは主体となり得るの?
泥酔者に対する保護責任がしばしば問題となっています。
これまで泥酔者に対する保護責任が認められた例としては、一緒に飲んでいて泥酔した仲間を、いったんは介抱されていたものの、その後放置して死亡させた事件や、タクシーの運転手が、タクシーの中で泥酔して寝込んだ客を、タクシーから降ろして路上に放置して死亡させた事件等があります。
これら過去の事件を考えると、自分の店で泥酔して寝込んでいる客に対して、店主であるAさんには保護責任があると考えるのが妥当ではないでしょうか。
遺棄とは?
保護責任者遺棄致死罪でいう「遺棄」とは、要保護者を場所的に移動させるだけでなく、置き去りのように、要保護者を危険な場所に遺留して立ち去る行為も含まれます。
Aさんのように、泥酔して店内で寝ているお客さんを店外に連れ出して放置している行為は「遺棄」に該当するでしょう。
保護責任者遺棄致死罪の法定刑は?
保護責任者遺棄致死罪は、刑法第219条に規定されている法律です。
保護責任者遺棄致死罪で起訴されて有罪が確定した場合は、刑法第218条に規定されている保護責任者遺棄罪の法定刑(3年以上5年以下の懲役)と刑法第204条に規定されている傷害罪の法定刑(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と比較して、重い刑が適用されるので、実質的な法定刑は「3カ月以上15年以下の懲役」となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、警察に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しています。
この初回接見サービスは、フリーダイヤル0120-631-881にて、年中無休、24時間でご予約を随時受け付けておりますので、いつでもご連絡ください。