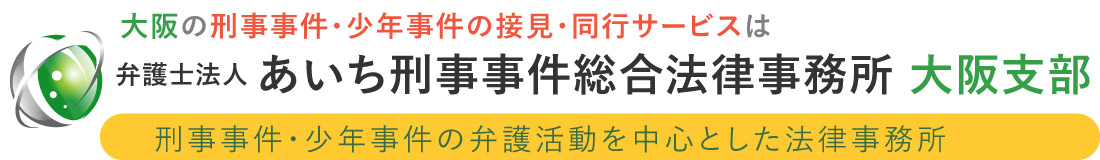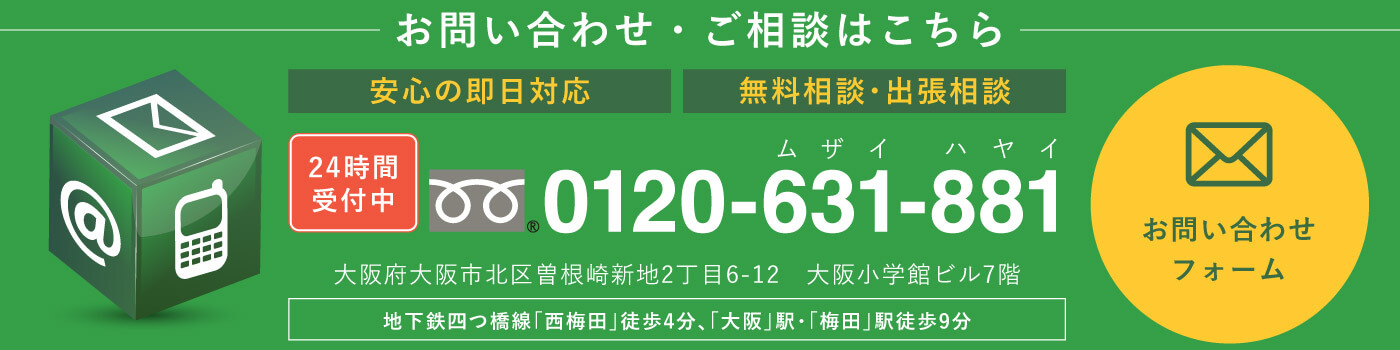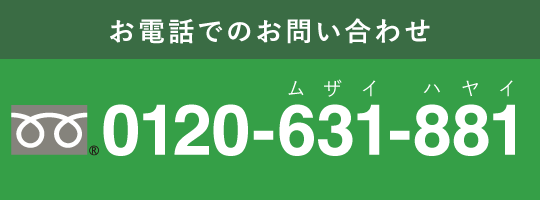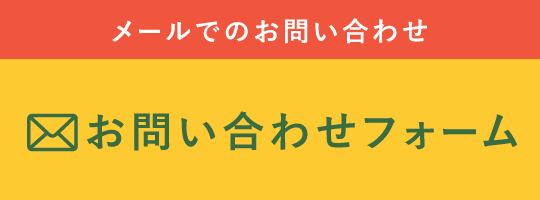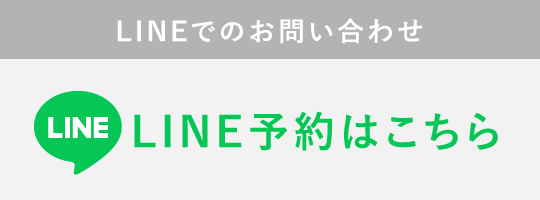※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。
裁判の種類
一般に「裁判」というと、法廷で裁判官・検察官・被告人・弁護士が集まり有罪無罪を決める一連の裁判手続を思い浮かべるかもしれません。
しかし、ここでいう「裁判」とは、裁判所や裁判官による法的な判断ないし意思表示のことをいいます。
裁判には、判決・決定・命令の3種類があり、これらは判断の主体や審理形式の違いにより区別されています。
判決
判決とは、法廷での口頭弁論の手続きを経て示される裁判所の判断のことです。
これには、必ず判断の理由をつけなければなりません。
判決について不服がある被告人・検察官は、控訴や上告を行います。
決定
決定とは、口頭弁論の手続きを必ずしも必要としないで示される裁判所の判断です。
判決と異なり、常に理由を付けなければならないわけではありません。
決定に対しては、抗告・即時抗告・特別抗告といった手段で不服を申し立てることができます。
※被疑者勾留の決定など第1回公判前の決定については、裁判官が行うことになるため準抗告による不服申し立てになります。
命令
命令とは、裁判官によって行われる判断のことです。
決定(裁判所が行う判断)と命令(裁判官が行う判断)は判断主体が異なります。
命令に対して不服がある者は、準抗告を申し立てます。
判決の分類
判決とは、裁判所が口頭弁論に基づいて示す判断のことを言いますが、判決にもいくつかの種類があります。
有罪判決
有罪判決は、検察官によって犯罪事実が証明された場合に、被告人に刑罰を言い渡す判決です。
有罪判決の中でも、執行猶予付きの判決と執行猶予が付いていない判決(実刑判決)があります。
さらに、刑の免除の判決も有罪判決の一つです。
刑の免除の判決は、被告人の行為について犯罪は成立するものの、法律で刑罰を免除するよう規定している場合に言い渡されます。
例えば、親族間の窃盗の特例の規定(刑法244条)などがあります。
無罪判決
一方、無罪判決は、法廷での審理の結果、被告人の行為は犯罪にならないと判断された場合、あるいは犯罪事実があったとの証明が不十分と判断された場合に言い渡されます。
なお、無罪判決を受けた被告人の損失を補償する制度として、刑事補償制度と費用補償制度があります。
刑事補償制度は、無罪判決を受けた被告人が身体拘束されていた期間に応じて金銭的な補償を請求できる制度です。
この制度は、無実であるのに身体拘束されていた人の不利益を補填することが目的ですから、無罪判決さえ受ければ誰でも受け取ることができます。
具体的な金額としては、1日あたり1000円~12500円の範囲で補償されます。
次に費用補償制度は、無罪を受けた被告人が裁判に要した費用の一部(出頭するのに要した旅費、日当及び宿泊料並びに弁護士報酬)を国が補償する制度です。
刑罰の種類
| 刑罰の名前 | 刑罰の内容の説明 | 刑の定めがある犯罪 |
| 死刑 | 絞首して執行します。死刑の言い渡しを受けた場合、執行まで刑事施設で留置されます。 | 殺人罪・強盗致死罪など |
| 拘禁刑 | 従来の懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰で、刑事施設(刑務所)に身体を拘束されます。改善更生を図るために必要な作業を行い又は指導を受けることになります。 | 刑法犯・特別法犯・条例違反などの多くの犯罪に規定 |
| 罰金 | 1万円以上の金銭を納付します。納付できなければ、労役留置場に留置され、働いて支払うことになります。 | 住居侵入罪・器物損壊罪など |
| 拘留 | 1日以上30日未満の期間身体を拘束されます。 | 公然わいせつ罪など |
| 科料 | 1000円以上1万円未満の金銭を納付します。納付できなければ、労役場に留置され、働いて支払うことになります。 | 器物損壊罪など |
| 没収 | 犯人が持っている犯罪に関わった財物を国庫に帰属させることです。財物を没収できない場合、代わりにその価額を追徴します。 | 刑法19条。全ての罪に適用あり。 |