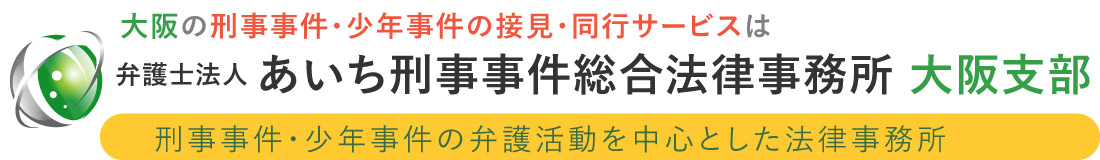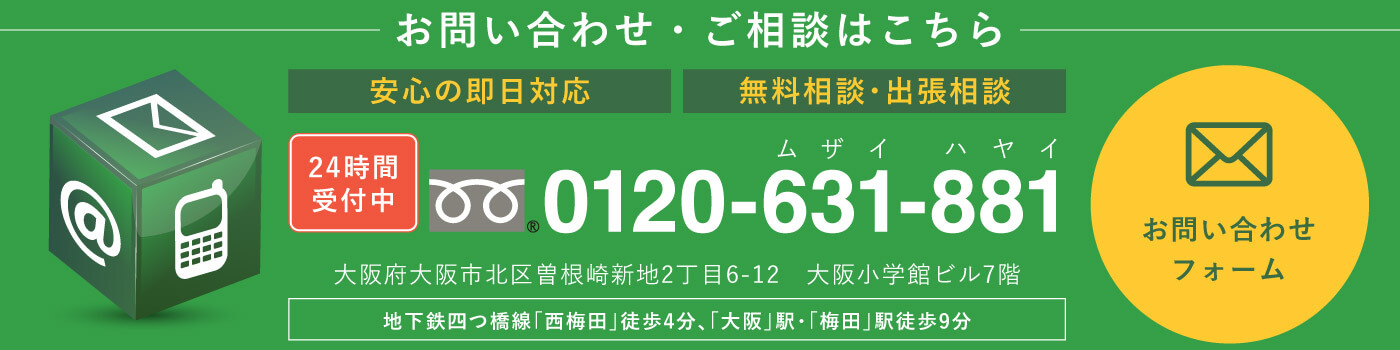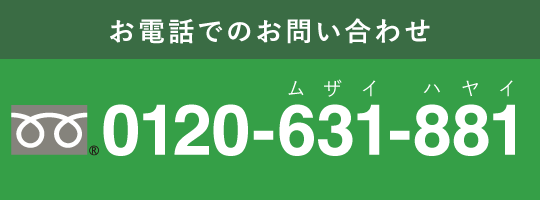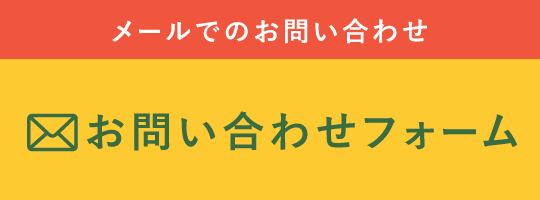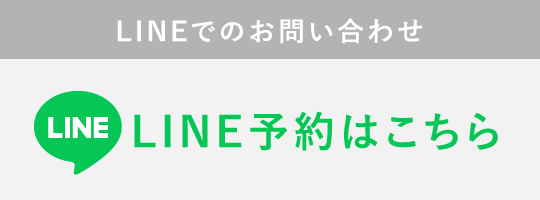Archive for the ‘刑事事件’ Category
お店の売上金を横領 業務上横領罪で住之江警察署に逮捕
売上金を横領したとして、業務横領罪で店長が住之江警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
Aさんは、全国にチェーン展開する大手外食産業で店長をしていましたが、売り上げを本部に過少申告し、その差額を、売上金を保管している金庫から抜き取る手口で、横領を繰り返していました。
そして1ヶ月ほど前に横領行為が会社に知れてしまうことになり、その後の会社の調査で横領額は600万円にも及びことが発覚したのです。
すでに横領したお金を全て使い果たしていたAさんは、その後、住之江警察署に業務上横領罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
売上金を着服
自己の占有する他人の物を着服すると「横領罪」となります。
そして着服した物が、業務上占有していた場合は「業務上横領罪」となります。
刑法第252条1項(横領罪)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の拘禁刑に処する。
刑法第253条(業務上横領罪)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
今回の事件、元店長が横領したのは、お店で保管していたお店の売上金です。
まずお店の売上金は、店長の物ではなく、そのお店を管理運営する会社の物です。
そして店長は、その売上金を保管、管理する立場にあるでしょうから、元店長が着服した売上金は、業務上横領罪でいうところの「業務上自己の占有する他人の物」に当たるでしょう。
ですから元店長の行為が「業務上横領罪」に該当することは間違いないでしょう。
ちなみに、もし売上金を着服したのが店長ではなく、単なるアルバイトだった場合はどうでしょう。
おそらくアルバイト従業員に、お店の売上金を保管、管理する権限は与えられていないでしょうから、業務上横領罪ではなく、刑法第235条に規定されている「窃盗罪」が適用されるでしょう。
業務上横領罪の量刑
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑です。
業務上横領罪の法定刑には、罰金刑が規定されていないので、起訴されて有罪が確定した場合、執行猶予を得ることができなければ実刑判決となり、刑務所に服役しなければなりません。
実刑判決を免れるには・・・
業務上横領罪で起訴されて有罪が確定した場合、どういった刑事罰が科せられるかは、横領額と被害弁償の有無が大きく影響します。
横領額が100万円を超えて、被害弁償がない場合は初犯であっても執行猶予を獲得できる可能性が低くなると言われています。
ですから実刑判決を免れるためには、いかに被害弁償できるかにかかっています。
すぐに弁償できない場合でも、支払計画を立て、弁償を約束することによって、会社側と示談を締結できることもあるので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
業務上横領事件の弁護活動に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、業務上横領事件に関する法律相談を初回無料で受け付けております。
無料法律相談をご希望のお客様は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
オンラインカジノで逮捕 常習賭博罪が適用
先日、オンラインカジノを利用したとして、常習賭博罪の疑いでテレビ関係者が逮捕された事件が報道されました。
1年ほど前からオンラインカジノが注目されて、これまで多くの芸能人やスポーツ選手等の著名人が警察に検挙されたり、検察庁に書類送検されて中には実際に刑事罰を受けた方もいます。
しかしこれまでオンラインカジノを利用したとして検挙された人たちに適用されていたのは、単純な賭博罪でしたし、警察に逮捕されたといった報道も聞いたことがありませんでした。
そこで本日のコラムでは、どうしてこのテレビ関係者が常習賭博罪で逮捕されたのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が検証します。
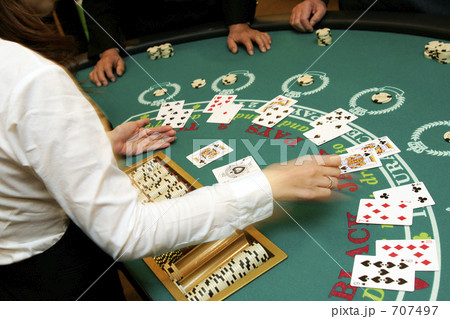
単純な賭博罪と常習賭博罪の違いは?
オンラインカジノを利用して賭け事をすれば刑法で規定されている賭博罪となります。
賭博罪には、単純な賭博罪(刑法第185条)だけでなく、常習賭博罪や賭博場開帳等図利罪(刑法第186条)があります。
単純な賭博罪と常習賭博罪の大きな違いは法定刑です。
単純な賭博罪は、50万円以下の罰金又は科料と、有罪になったとして科せられる刑罰は財産刑のみで刑務所に収容されることはありません。
しかし常習賭博罪は、3年以下の拘禁刑と、単純な賭博罪とは逆で、罰金等の財産刑の規定がないので、起訴される刑事裁判で裁かれることとなり、そこで有罪が確定すると執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。
警察に逮捕されるの?
単純な賭博罪については法定刑こそ軽いものですが、罰金刑の上限が50万円ですので警察に逮捕されないとは限りません。
ただ常習賭博罪と比べると逮捕されるリスクは低いでしょうし、逮捕されたとしても事実を認め、証拠がハッキリとしている場合は比較的早い段階で釈放されると思われます。
常習賭博罪となるケースは?
捜査当局が常習賭博罪で立件するには、常習性を裏付ける必要があります。
常習性の裏付けには、賭博行為をした回数だけでなく、賭けた金額や、賭け事の内容、そして賭博罪の前科前歴の有無などが考慮されます。
今回の事件で逮捕されたテレビ関係者は、テレビ局の社内調査が行われた後も賭博行為を続けており、さらに賭けた金額も1億円にのぼると報道されていることを考えると、常習性が裏付けられての逮捕となったのではないでしょうか。
(参考記事はこちら)
賭博罪で摘発されると
今後もオンラインカジノを利用しての賭博行為に対する摘発が続くことが予想されます。
ある日急に警察から呼び出しがあったり、急に逮捕されることもあるかもしれません。
オンラインカジノを利用して賭博行為をしてしまった過去がある方は、早めに弁護士に相談しておくことをお勧めします。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
ネット通販を装い代金詐取 詐欺罪で逮捕
大阪府大阪市西区で、通販サイトを装い商品代金を騙し取ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪府大阪市西区に住むAさんは、人気のゲーム機やブランド品を定価より安く販売しているかのように装う、架空の通販サイトを開設しました。
サイトには実在する企業のロゴや写真を転載し、あたかも正規の販売店であるかのように見せかけており、購入希望者からは銀行振込で代金を受け取っていました。
被害者であるVさんは、SNS広告を通じてそのサイトにアクセスし、約8万円のゲーム機を注文して代金を振り込みましたが、商品は届かず、連絡も取れなくなりました。
不審に思ったVさんが大阪府西警察署に相談したことで捜査が開始され、サーバーのアクセスログや振込口座の名義などから、Aさんがサイトの運営者であることが特定されました。
その後、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
詐欺罪
詐欺罪とは
詐欺罪は刑法第246条に規定されており、条文は以下の通りです。
第二百四十六条(詐欺)
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は、大まかに言えば、人を欺いて財物を交付させ、不法に利益を得る犯罪です。
2項は、詐欺利得罪という罪を規定しており、2項詐欺などと言われています。
詐欺罪が成立するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
①欺罔行為(欺く行為)
欺罔行為とは、相手方が真実を知っていれば財産的処分行為を行わないような重要な事実を偽ることをいうとされています。
詐欺罪において最も重要な要素は、この「欺く行為」と言ってよいでしょう。
Aさんの場合、架空の通販サイトを解説し、あたかも正規の販売店であるかの装ったことがこれに該当します。
②錯誤
詐欺罪における錯誤とは、財産的処分行為をするように動機付けするものであれば足りるとされています。
今回の事例では、Vさんは、Aさんのサイトからゲーム機を購入できると思い、実際に注文していることから、Vさんが錯誤に陥っていたと認められる可能性が高いと言えます。
③交付行為
詐欺罪の成立には、交付行為が必要です。
今回の事例では、Vさんは代金を振り込んでおり、これが交付行為に当たります。
④財産上の損害
詐欺罪の成立には、財産的損害の発生も必要となります。
詐欺罪も財産犯である以上、実質的な財産的損害が必要であり、被害者の意図した交換の失敗が必要であるとされています。
今回の事例では、Vさんはゲーム機を受け取れると思い代金を振り込んだにもかかわらず、商品が届かなかったため、意図した交換の失敗があり、財産的損害が発生したと言えるでしょう。
弁護士に相談するメリットと事務所のご案内
早めに弁護士を付けることで、早期に示談交渉を開始することができる・早期保釈の可能性が高まるなど様々なメリットがあります。
相談を受けたタイミングが早ければ、それだけ時間的な余裕が生まれ、より充実した弁護活動を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
詐欺事件を含め、幅広い刑事事件の対応実績があります。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談ご予約・初回接見のご依頼を受け付けています。
フリーダイヤル:0120-631-881
詐欺事件その他刑事事件・少年事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
線路への立ち入り 問われる刑事責任は?
走行中の電車を撮影する人たち、いわゆる「撮り鉄」の一部による迷惑行為によって、電車が運転を一時見合わせるなど、電車の運行にまで影響が出ることがあるようです。
先日も、東北地方を走行中の電車の運転士が線路内に立ち入っている撮り鉄を発見し、遅延や運休など電車の運行に影響が出たことが報じられました。

こういった撮り鉄の迷惑行為が刑事責任に問われることはあるのでしょうか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
線路内に立ち入ると
線路内に立ち入る行為は鉄道営業法違反となるでしょう。
鉄道営業法第37条では、停車場そのほか鉄道地内にみだりに立ち入る行為を禁止しているからです。
ただ罰則規定に非常に軽いもので「科料」です。
鉄道営業法違反で逮捕は難しい
先述したように線路内に立ち入ったとして鉄行営業法違反で有罪となったとしても科せられる刑事罰は「科料」です。
このような軽微な犯罪については、定まった住居がない場合や、逃走のおそれがある場合、出頭に応じない場合を除いては逮捕できないと定められています。(刑事訴訟法199条1項、同法213条)
ですから警察が、線路内に立ち入った撮り鉄を鉄道営業法違反で逮捕するのは難しいと言えるでしょう。
しかし逮捕できなくても在宅で警察の捜査を受け刑事責任に問われる可能性は十分にあります。
別の犯罪に抵触する可能性もある
威力業務妨害
線路内に立ち入ることによって、走行中の電車を停止させたり、その影響によって電車の運行に影響を及ぼし、鉄道会社の営業を妨害したとみなされると威力業務妨害罪に問われる可能性があります。
威力業務妨害罪の罰則は、鉄道営業法違反とは違い、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と厳しいものなので、逮捕される可能性も十分に考えられます。
往来危険罪
もし線路内に立ち入ったことによって列車の往来に危険を生じさせると往来危険罪に問われる可能性があります。
往来危険罪は、過失の場合も過失往来危険罪として刑事責任を問われるので注意が必要です。
往来危険罪の法定刑は2年以上の有期拘禁刑ですが、過失往来危険罪の場合は、30万円以下の罰金です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では刑事事件に関するご相談をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。
刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【守口市の事件】コインパークで顔面から出血の男性 事件・事故で警察が捜査
守口市のコインパーキングで顔面から出血した男性が倒れているのが見つかり、守口警察署が事件と事故の両面から捜査を行っています。
本日のコラムは、報道されているこの事件(事故)を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部がまとめました。
本日のコラムは、産経新聞 等の記事を参考に作成しています。
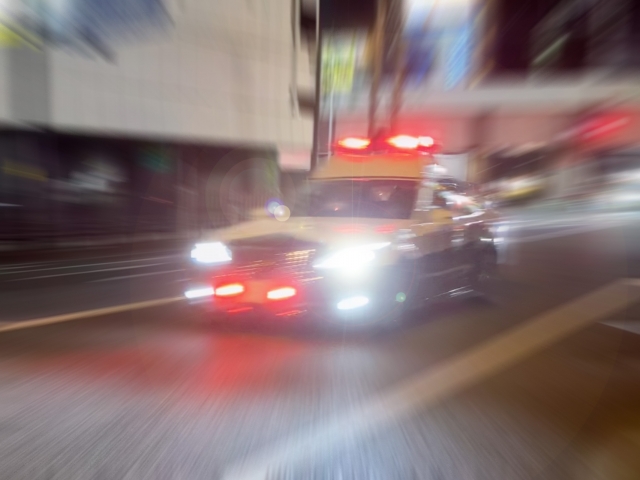
事件の概要
6月13日午前8時15分ころ、大阪府守口市日吉町1丁目のコインパーキングで、30代の男性が顔面から出血し倒れているのが見つかり、救急搬送されました。
男性は、落ちていた身分証等から旭区内に住む男性と判明しましたが、話せる状態ではなく被害の詳細は明らかになっていません。
通報を受けた守口警察署は事件と事故の両面から捜査しています。
事件なのか事故なのか
男性が発見された場所がコインパーキングであることを考えると、誰かに暴行されて怪我をしたという事件性があるものなのか、車にはねられて怪我をしたとう事故なのか報道だけで判断するのは難しいでしょう。
ただ男性の財布等が落ちていたということですので、財布内に現金等金目の物が残されていたとするならば強盗など物盗りの犯行である可能性は低いでしょう。
また現場を地図で確認したところ、現場は非常に交通量の多い国道1号線のすぐ近くの一方通行に面したコインパーキングで、守口警察署からはわずか350メートルしか離れていません。
京阪電鉄の守口市駅や土居駅、地下鉄の太子橋今市駅もすぐ近くにあり、決して人通りが少ない場所ではないように思われます。
また発見時間が午前8時15分という通勤時間帯であることを考える、事件や事故の発生直後に発見された可能性よりも、発生から相当時間が経過して発見されたと考える方が自然ではないでしょうか。
ただコインパーキング内に財布が落ちていたとされることから考えると、発見されたコインパーキング内で、何らかの事件や事故が起こった可能性が高いかと思われます。
警察の捜査は?
男性本人が話しを聞ける状態ではないようですので、警察は、目撃者を探したり、付近の防犯カメラ映像を確認して、まずは事件性の有無や、犯罪を特定し、その上で事件性があると判断すれば犯人を捜査します。
コインパーキング内ですので、防犯カメラが必ず設置されているでしょうからこういった捜査には時間がかからないかと思います。
コインパーキング内に財布が落ちていたとされることから考えると、発見されたコインパーキング内で、何らかの事件や事故が起こった可能性が高いかと思われますが、もし男性が被害にあったのち、自力で移動してこのコインパーク内までたどり着いていたとすれば事件や事故の特定まで時間がかかるかもしれません。
ただ最近は、街じゅういたるところに監視カメラや、防犯カメラが設置されているので、どういった事情があるにしても、事件や事故を特定するまでさほど時間はかからないでしょう。
刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では刑事事件に関するご相談を年中無休で受け付けております。
無料法律相談をご希望の方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
非常停止ボタンを押下 電車を止めた男が逮捕
踏切の非常低所ボタンを押下して走行中の電車を停止させた男が警察に逮捕されました。
警察に威力業務妨害で逮捕された男は「いたずら感覚でボタンを押しました」と容疑を認めているようです。
(こちらの記事を引用しています。)
電車の緊急停止
踏切に設置されている非常停止ボタンが押下されると、付近を走行中の電車は一斉に停止し、その後、駅員等が安全確認を行わなければ運転を再開できません。
電車の運行は分刻みの厳格な時間管理がなされており、数分の停止によってその先の電車の運行時間に遅れが生じ、多くの利用客に影響が及びます。
必要がないのに非常停止ボタンを押下する行為は、決していたずらでは済まされない非常に悪質な行為です。
威力業務妨害罪って?
人の業務を故意的に妨害すると刑法に規定されている業務妨害罪が適用されます。
業務妨害罪には、威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪があり、今回の事件では威力業務妨害罪が適用されています。
この二つの業務妨害罪の違いは、業務妨害する方法が異なります。
威力を用いれば威力業務妨害罪となり、偽計を用いた場合は偽計業務妨害罪になるのですが、罰則はともに、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
刑事罰だけでなく被害者から損害賠償請求されることも・・・
今回の事件で逮捕された男には同様の余罪が疑われているようですが、複数の業務妨害罪で有罪が確定したとしても、初犯であれば実刑判決まで下される可能性は低いのではないでしょうか。
それよりも、鉄道会社から多額の損害賠償を請求される可能性があるので、経済的な損失の方が大きいかもしれません。
業務妨害行為でお店等から多額の損害賠償を請求されるケースは、最近よくニュース等で報道されている飲食店に対する業務妨害行為ではよくあることです。
数千万円を請求されたケースも
数年前に起こった大手回転すしチェーンにおいて発生した業務妨害事件では、事件を起こした犯人に対してお店側が6,700万円もの損害賠償を請求しています。
この民事訴訟は、最終的に調停によって和解が成立したようですが、大手企業は迷惑行為に対して厳正に対処する傾向があるので、ちょっとしたいたずらでは決して済まされないので注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では刑事事件に関するご相談のご予約を年中無休で受け付けております。
フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
すれ違いざまに身体を触る 不同意わいせつ罪で逮捕
大阪府茨木市で、すれ違いざまに通行人の身体を触ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
大阪府茨木市の駅前の路上で、Aさんが見知らぬ女性Vさんとのすれ違いざまに、Vさんの胸を触ったとされる事件が発生ました。
驚いたVさんがその場で「やめてください」と声を上げ、近くにいた通行人が警察に通報しました。
通報を受けて茨木警察署の警察官が現場に急行し、Aさんは不同意わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「たまたま手が当たっただけで、わざとではなかった」と供述しているとのことです。
一方で、Vさんは「目が合った直後に、突然胸を触られて怖かった」と話しており、警察は事件当時の状況について詳しく捜査を進めています。
現場には防犯カメラが設置されており、映像の確認も行われるとのことです。
(事例はフィクションです。)
不同意わいせつ罪とは
不同意わいせつ罪は刑法176条に規定されており、176条1項各号に掲げられている暴行・脅迫、アルコール、社会的関係などの事由により、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をする犯罪です。
今回の事例では、Vさんの供述によると、Aさんはすれ違いざまにAさんの胸を触ったとされています。
このような状況は、同項5号の「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない」に該当することになるでしょう。
すれ違いざまに突然胸を触る場合などは、まさに同項5号の典型的な場面とされています。
また、「わいせつな行為」とは、被害者の性的自由を侵害するに足りる行為とされています。
今回の事例のような状況で、胸などを触る行為は「わいせつな行為」に当たるとされるでしょう。
不同意わいせつ罪での弁護活動
不同意わいせつ罪における主な弁護活動として、以下の3つが挙げられます。
①一刻も早い示談活動
不同意わいせつ罪は、被害者の告訴がなくても起訴される非親告罪ですが、早急に示談を行うことで事件化を防ぎ、不起訴処分の可能性を高めることができます。
もし起訴されてしまった場合でも、示談を成立させることで執行猶予付きの判決を得られる可能性が高まります。
また、示談の成立は身柄の釈放や社会復帰にも有利に働きます。
②無罪・無実の主張
わいせつ行為をしていない場合や相手の同意があった場合には、弁護士を通じて証拠の不十分さを主張し、不起訴処分や無罪判決を目指していくことになります。
③早期釈放
逮捕・勾留されてしまった際は、弁護士が検察官や裁判官に働きかけることで、早期釈放を目指します。早期釈放により、早期の社会復帰を実現する可能性を高めます。
刑事事件に強い弁護士に相談を
不同意わいせつ罪で逮捕された場合、その後の対応次第で処分が変わる可能性があります。
適切な対応をすることで、不起訴処分を獲得し、前科を避けることができる可能性もあれば、適切対応ができず、不利な結果を招いてしまう可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件に関する豊富な知識・経験を持つ弁護士が、依頼者の状況に応じて弁護活動に尽力致します。
また、当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料法律相談のご予約、逮捕・勾留されている方に弁護士を派遣する初回接見のご依頼を受け付けております。
フリーダイヤル:0120-631-881
刑事事件でお困りの方やそのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にぜひご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
その気はあると思った…不同意わいせつ等性犯罪の現状
その気があると思ってわいせつ行為に及んだ女性に訴えられて不同意わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、マッチングアプリで知り合った女性と2ヶ月ほどメールや電話でやり取りした後に実際に会うことになり、先週末、二人でお酒を飲みに行きました。
お酒の席では話しが盛り上がり、その後、カラオケに行くことになり二人は、大阪市北区のカラオケBOXに移動しました。
そこでAさんは、女性が自分に好意を抱いてくれていると思い込み、女性の方に手を回して抱き寄せながらキスをしたのです。
そしてその後も、服の上からではあるものの胸を触ったり、お尻を触ったりするわいせつ行為に及んだところで女性が「トイレに行く」と言って部屋を出ていき、そのまま女性は帰宅してしまいました。
それから数日して、Aさんのもとに女性から「警察に訴えました」とメールが送られてきて、実際にAさんは不同意わいせつ罪で大阪府曽根崎警察署に逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)
昨年、刑法が改正されて、不同意わいせつ罪や、不同意性交等罪が新設されましたが、不同意わいせつ罪や、不同意性交等罪は、それまでの性犯罪を規制する法律と比べると成立要件の幅が広がり、改正前までは警察沙汰になったり、逮捕までされなかったような行為でも警察が捜査を開始したり、逮捕されてしまう方が増加傾向にあるようです。
不同意わいせつ罪
今回Aさんが逮捕された不同意わいせつ罪について解説します。
不同意わいせつ罪は、刑法改正にともなってそれまでの「強制わいせつ罪」に代わって新設された犯罪です。
不同意わいせつ罪は、簡単にいうと、相手の同意なくわいせつな行為に及ぶと成立する犯罪です。ここでいう「相手の同意がない」とは、相手がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
これまでの強制わいせつ罪は、暴行や脅迫をもちいてわいせつ行為に及ぶと成立していたので、その判断基準は明白でしたが、不同意わいせつ罪は、被害者の同意があったか否が判断基準となるため、被疑者と被害者の二人きりで発生した不同意わいせつ事件の場合は、被害者の供述以外に客観的な証拠が乏しくなる可能性があるでしょう。
同意がないとは
不同意わいせつでいうところの「同意がない」とは、相手(被害者)がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
条文には、この同意がない状況を8つの項目に分けて明記しています。
①暴行・脅迫を用いた性交等
②心身の障害を用いた性交等
③アルコール・薬物の影響を用いた性交等
④睡眠その他の意識不明瞭を用いた性交等
⑤同意しない意思の形成・表明・全うするいとまがない状態
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させた性交等
⑦虐待に起因する心理的反応を用いた性交等
⑧経済的・社会的関係上の地位を用いた性交等
不同意わいせつ罪の刑事責任
また不同意わいせつ罪の法定刑は強制わいせつ罪と同じ「6か月以上10年以下の拘禁刑(※拘禁刑の運用が始まるまでは懲役刑)」です。
不同意わいせつ罪で逮捕されると
不同意わいせつ罪で警察に逮捕された場合は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士からアドバイスを受ける必要があるでしょう。
ご家族、ご友人が不同意わいせつ罪で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスをご利用ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【薬物事件】知人に対して覚醒剤を使用 覚醒剤取締法違反で逮捕
【薬物事件】知人に対して覚醒剤を使用したとして、覚醒剤取締法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

【薬物事件】知人に対して覚醒剤を使用して逮捕
Aさんは10年以上前に覚醒剤取締法違反(所持及び使用)で有罪判決を受けた犯歴がありますが、それ以降Aさんは、覚醒剤から足を洗い全うな生活をしていました。
しかし2カ月ほど前に知人から「覚醒剤を射ってくれ」と頼まれたので、知人の腕に覚醒剤を射ってあげました。
その時は、知人が自分で用意した注射器と覚醒剤を射ってあげただけでAさんは使用していません。
それから数日して、この知人が警察官の職務質問を受けて覚醒剤の使用が発覚してしまい、そのまま大阪府枚方警察署に逮捕されたようです。
そして今朝、Aさんのもとにも、大阪府枚方警察署の捜査員が訪ねてきて、Aさんは覚醒剤の使用容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
覚醒剤取締法違反
覚醒剤取締法では、覚醒剤の所持や使用、譲渡や譲受、輸出入等を禁止しています。
覚醒剤の所持や使用、譲渡や譲受の法定刑は、営利目的の場合「1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科」ですが、営利目的ではない場合「10年以下の懲役」です。
人に対して覚醒剤を使用すると
覚醒剤取締法では、覚醒剤の使用について
第十九条 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
一 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
二 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
三 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
四 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五 法令に基づいてする行為につき使用する場合
と定め、覚醒剤の使用を禁止しています。
覚醒剤の使用方法については特段の規定はありません。
代表的な使用方法は、注射したり、吸引する方法が挙げられますが、中には口から飲んだり、身体の粘膜の薄い部位に塗り込む方法で使用する方法もあります。
これらの方法で自分自身が覚醒剤を使用するだけでなく、Aさんのように自分以外の第三者の使用を手伝っても使用罪に問われます。
覚醒剤取締法違反で逮捕されるとどうなるの?
覚醒剤取締法違反で警察に逮捕されると勾留される可能性が高いといえます。
勾留期間は10日~20日で、この期間中は留置施設での生活を強いられることとなり、裁判官が勾留と共に接見禁止を決定した場合は、勾留期間中の面会や差し入れが制限されることがあります。(弁護士は例外)
また、覚醒剤取締法に限らず、違法薬物を所持や使用等した容疑で警察に逮捕されると必ずと言って程の確率で採尿されて、違法薬物を使用してかどうかを検査されます。
逮捕後の採尿によって違法薬物の使用が発覚した場合、新たな犯罪事実として事件化される可能性が高く、場合によっては再逮捕の理由になってしまいます。
薬物事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件専門の法律事務所です。
覚醒剤取締法違反等の薬物事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
またご家族や、ご友人が薬物事件を起こして警察に逮捕された方には、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。
初回接見サービスについては
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
女子高校を盗撮 性的姿態等撮影罪で逮捕
大阪府東大阪市で、高校生のスカート内を盗撮したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
大阪府東大阪市の駅構内で、女子高校生であるVさんが階段を上っていた際、背後にいたAさんがスマートフォンをVさんのスカートの中に向けて撮影していたところを、駅員が目撃しました。
駅員は、すぐさま河内警察署に通報しました。
通報を受けて駆けつけた警察官によって、AさんのスマートフォンにVさんのスカート内を撮影した動画が保存されていることが確認され、Aさんはその場で逮捕されました。
Aさんは取り調べに対し「好奇心でやってしまった」と供述しているとのことです。
(事例はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪とは
従来、スカート内を盗撮するといった盗撮行為は、各都道府県が定める迷惑防止条例などにより処罰されていました。
しかし、迷惑防止条例は、各都道府県により処罰範囲が異なることなど不十分な点を抱えているとの指摘がありました。
そこで、2023年に性的姿態撮影等処罰法(正式名称は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が施行され、盗撮行為の厳罰化が行われました。
性的姿態等撮影罪は性的姿態撮影等処罰法第2条1項に定められており、その法定刑は「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」となっています。
また、同条2項により、性的姿態等撮影罪は未遂も処罰対象となっています。
性的姿態等撮影罪では、正当な理由なく、ひそかに、性的な部位などを撮影することが処罰されます。
今回のAさんのした行為には、正当な理由となる事情はなく、性的姿態等撮影罪が成立することとなるでしょう。
盗撮事件における示談の重要性
性的姿態等撮影罪などの盗撮事件においては、示談の成立が不起訴処分の獲得に大きな影響を与えます。
起訴され、有罪判決を受けると、懲役刑や罰金刑だけでなく、社会的信用を失うリスクもあります。
つまり、示談交渉の成否が重要になります。
もっとも、示談交渉は当事者でもできますが、性的姿態等撮影盗撮罪など性犯罪の事案では、被害者が加害者に連絡先を教えてくれないなど、示談交渉に応じてくれない可能性も高く、仮に被害者の方と会うことができたとしても、かえって恐怖心や怒りを増大させてしまうことも大いに考えられます。
しかし、守秘義務が課せられている弁護士を付けることで、示談交渉に応じてもらえることも少なくありません。
したがって、不起訴処分獲得のために重要な示談交渉は、直接当事者同士で行うよりも、法律のプロである弁護士に依頼するのが望ましいということになります。
まずは弁護士に相談を
以上見てきたように、盗撮事件においては、示談成立に向け迅速に対応することが望ましく、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような盗撮事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、
0120-631-881
にて24時間365日受付中です。
大阪府で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。