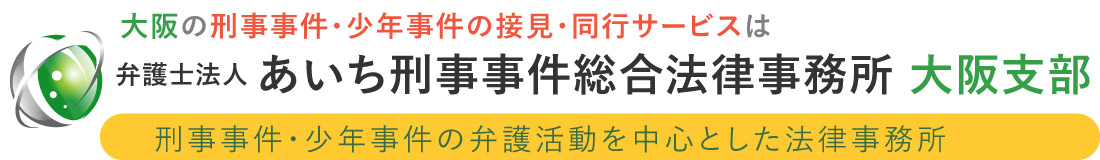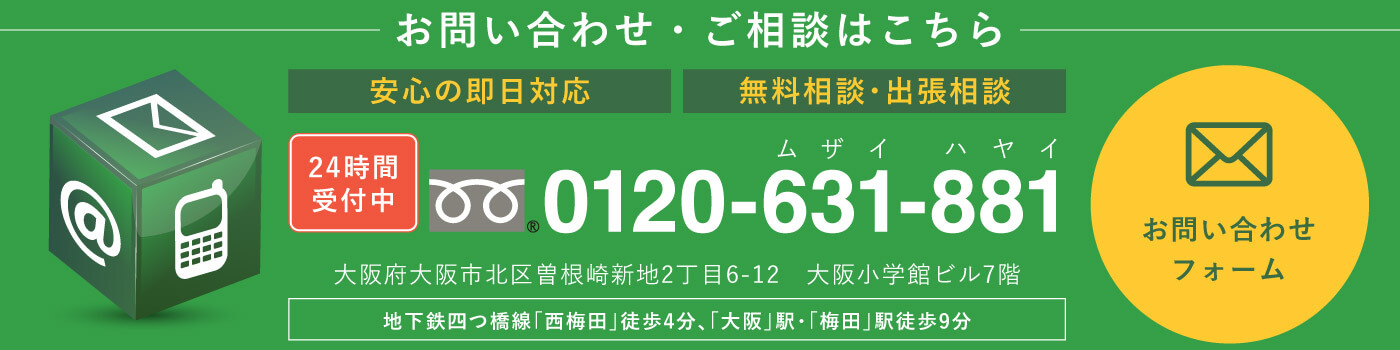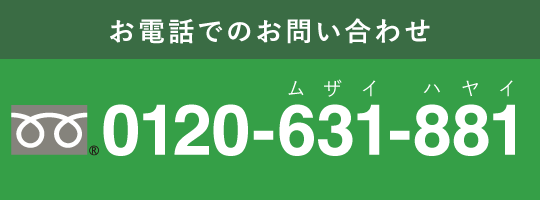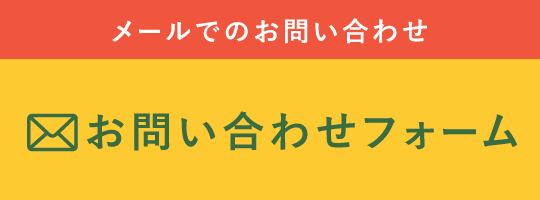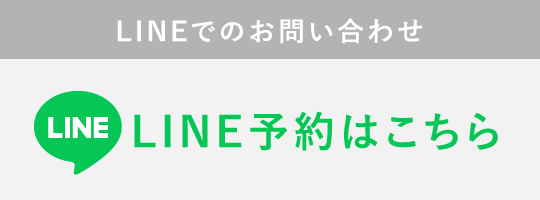Author Archive
【お客様の声】会社の同僚とトラブル 器物損壊の容疑で取調べを受けるも…大きく進展することなく終結
本日は、会社の同僚に対して器物損壊事件を起こした容疑で警察で取調べを受けていた男性の事件の弁護活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部がご紹介します。
◆事件内容と経過◆
男性は、勤めている会社の同僚に対して器物損壊事件を起こしたとして警察に呼び出されて取調べを受けましたが、警察は決定的な証拠がない状況で、男性に自白を迫っていました。
警察の取調べに対して大きなストレスをかかえていた男性は、自分の味方になってくれる弁護士を探して弊所の無料相談を利用されました。
男性から詳しい話しを聞いた弁護士は、精神的な支えとなって男性をサポートしました。
その結果、男性の事件は発覚から半年近く経過しても大きく進展することなく手続きを終えました。
◆結果◆
不送致
◆解説◆
警察で取調べを受けている方のほとんどは「今後どうなってしまうのか・・・。」「何か厳しい処分になるのではないか・・・。」といった不安を感じながらも、誰にも相談できず孤独と戦っています。
そんな方を精神的な面からサポートし、支えられるのは弁護士しかいません。
今回の弁護活動においても、男性から警察でどういった取調べを受けているのか、取調べの内容を詳しく聞くことによって、警察が決定的な証拠がない状況で男性に自白を迫っていることが分かりました。
弁護士は警察の取調べに対するアドバイスを徹底して行い、男性が厳しい取調べに屈することがないようにサポートしました。
その結果、事件発覚から半年近く経過しても大きく進展することなく手続きを終えることができたのです。
今回の弁護活動は、警察や検察等の捜査当局や、裁判所に対して行うだけではなく、精神的な面で依頼者を支えることも、大切な刑事弁護活動だと感じた事件でした。
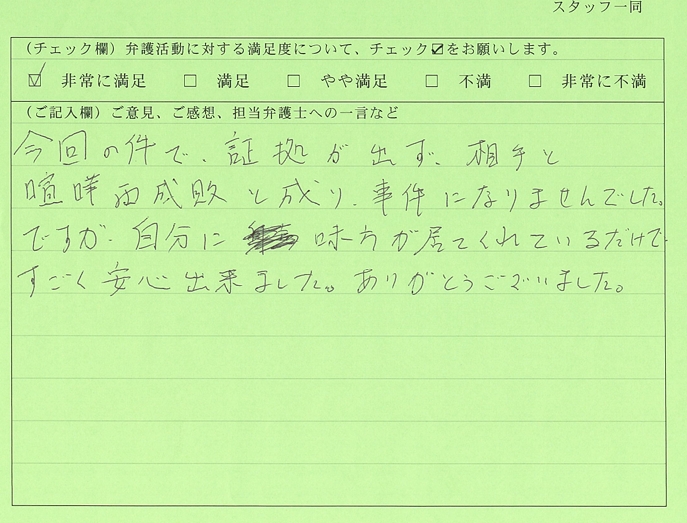
刑事事件に関するご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間・年中無休)
までお気軽にお問い合わせください。
【お客様の声】万引きで観護措置決定の少年 観護措置決定の取消しに成功
本日紹介するお客様の声は、万引きの事実で観護措置が決定し少年鑑別所に収容されていた少年の事件です。
観護措置決定の取り消し請求が容認され、少年院送致を回避した弁護活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部がご紹介します。
◆事件内容と経過◆
少年は、以前、友人と共にバイクを盗んだ非行行為で少年審判を受けていました。
その際に、友達関係を見直し更生することを約束していましたが、その後、今回の万引き事件を起こしてしまいました。
警察による捜査期間中は逮捕等によって身体拘束を受けることがなかった少年ですが、家庭裁判所に送致後に観護措置が決定して少年鑑別所に収容されてしまいました。
観護措置決定後に選任された弁護士は、家庭裁判所に観護措置決定の取消しを求め、その請求が認められて家族のもとに帰れた少年は、弁護士のサポートを受けながら反省を深め、家族と共に更生に向けて取り組みました。
その結果、少年は保護観察処分となり少年院送致を免れることができました。
◆結果◆
観護措置決定の取消し
保護観察
◆解説◆
今回の弁護活動は、すでに観護措置が決定し、少年鑑別所に収容されてから開始したため、まずは少年を家族のもとに帰れるように観護措置決定の取消し請求を行いました。
ただ少年は、短期間の間に、同じ友達と共に事件を起こしていたことから、ご家族には、少年の生活を見直し、厳しい監視監督の体制を整えることが必要でした。
また少年は、再犯を犯してしまったものの、更生に向けては意欲的に取り組んでおり、少年鑑別所での生活によって通っている学校の進学等にも影響が及んでしまう可能性がありました。
弁護士は、そういった事情を裁判官に訴えて観護措置の取消しを請求したのです。
その結果、少年の観護措置は取り消されて家族のもとに帰ることができました。
それからは、少年との面会を繰り返し、少年審判に向けての準備を行いました。
少年には、これまでの生活や、友人関係を見直してもらうなど、反省の情を深めてもらうだけでなく、ご家族にも少年の更生に向けて取り組んでいただいたのです。
その結果少年は、少年院送致を免れ、保護観察処分となりました。
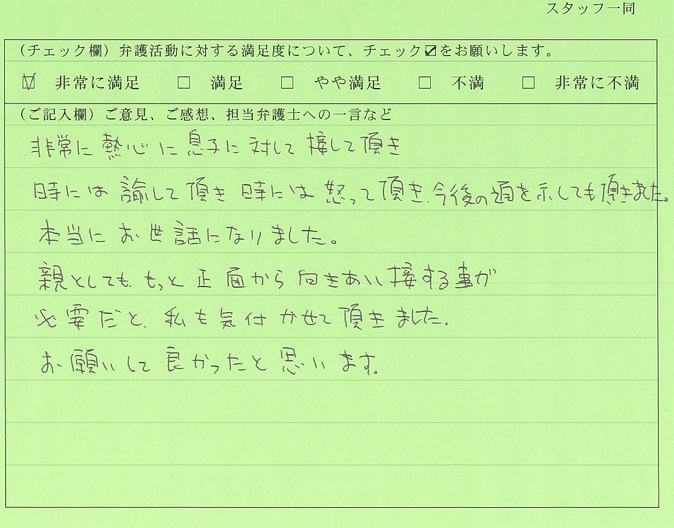
少年事件に関するご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間・年中無休)
までお気軽にお問い合わせください。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集2025
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2025年(令和7年)度の司法試験又は予備試験の受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所のアルバイトスタッフ(事務アルバイト)を求人募集します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生は是非ご応募下さい。

司法試験・予備試験受験生アルバイトについて
司法試験又は予備試験受験生が司法試験に最終合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に司法試験・予備試験の受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件及びその関連事件の弁護活動を間近に見ることができます。試験勉強で学んだ法律知識が弁護士の弁護業務の中でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をすることができます(深夜早朝手当も出ます)。
当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場で、司法試験・予備試験受験生にはうってつけのアルバイトです。
司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人情報
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための育成研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある方も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の例)】
・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※個人の事情と業務内容に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【執務環境】
・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事事件、少年事件の専門性が高い職場
【勤務地】
弁護士法事人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、最寄りの西梅田駅から徒歩5分、大阪・梅田駅からも徒歩9分程度という各方面からの通勤アクセスが非常に良い場所にあり、隣接する京都支部、神戸支部と連携して、関西圏全域の法律相談や初回接見に対応しています。
取り扱う事件は、大阪地方検察庁や大阪地方裁判所が管轄する大阪市内・大阪府内の刑事事件・少年事件を中心に兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県といった関西全域にも及ぶ広範囲の刑事事件・少年事件を取り扱うことになるため、事件種類も多様であり、刑事事件・少年事件専門の弁護士による刑事弁護活動や付添人活動を間近に見ることができます。
勉強しているだけではわからない刑事弁護活動の実務を間近で見ることができますので、試験突破に向けた勉強のモチベーションにもつながります。
法律事務所の仕事や雰囲気を通じて社会人経験を積める環境でのアルバイトは、法曹界を目指す若い世代の方々にとって、とても有意義な時間となることは間違いありません。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問ください。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
なお、ご応募から1週間以上経過しても当事務所採用担当者から連絡がない場合、お申込が確認できていない可能性がございますので、お手数ですが当事務所まで直接電話にてお問い合わせ下さい。
女性に付きまとい 軽犯罪法違反で検挙された事件
町で見かけた女性に付きまとったとして、軽犯罪法違反(つきまとい)の容疑で、警察の事情聴取を受けた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
Aさんは、町で見かけたタイプの女性の後ろを、約30分間、約1キロメートルにわたってつきまとったとして、後日、大阪府天満警察署に呼び出されて、軽犯罪法違反の容疑で事情聴取を受けました。
Aさんは「タイプだったのでつきまといたくなった」と軽犯罪法違反(つきまとい)の容疑を認めています。
(実話をもとにしたフィクションです。)
軽犯罪法違反(つきまとい)
軽犯罪法1条28号では、「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」「は、これを拘留又は科料に処する」と規定されています。
軽犯罪法1条28号における「つきまとった」行為とは、執拗に人を追随することをいいます。
参考事件の、Aさんの行為は執拗に被害者を追随する行為であるといえ、軽犯罪法1条28号における「つきまとった」行為に該当すると考えられます。
そして、軽犯罪法1条28号における「不安」とは、生命・身体などに対して何らかの危害が加えられるのではないかという危惧・心配のことをいいます。
また、軽犯罪法1条28号における「迷惑」とは、恥辱感を覚えたり、その場の秩序を乱していると思ったりする感情を与えることをいいます。
さらに、これら軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑」を「覚えさせるような仕方」とは、現実に他人に軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑」を覚えさせることを必ずしも要しないと考えられています。
すなわち、具体的な事情に照らして通常人が軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑」を覚えると認められるような方法であれば、軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方」に該当すると考えられています。
具体的事情としてはつきまとい行為の目的・態様、つきまとい行為の行為者の性別・年齢、つきまとい行為の被害者の性別・年齢などが挙げられます。
不起訴を目指す弁護活動
軽犯罪法違反(つきまとい)の容疑で捜査を受けている場合において不起訴処分の獲得を目指す場合、被害者と示談をすることが重要となります。
また、性的な目的でなされた軽犯罪法1条28号のつきまとい行為は、性犯罪と密接していると考えられがちです。
そのため、メンタルクリニックに通うなどして再犯を繰り返さないようにすること、そしてそのような再犯防止対策をとっていることなどを検察官に上申することも重要となります。

つきまとい行為は、事情が異なればストーカー規制法違反や各都道府県の迷惑防止条例違反といった別の犯罪が成立する可能性もあるため、早めに弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
軽犯罪法違反(つきまとい)の罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
大阪市の軽犯罪法違反(つきまとい)事件で任意の取調べを受けた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。
盗品バッテリーを買い取り 盗品等有償譲受で逮捕
盗品の電動自転車用バッテリーを買取ったとして、盗品等有償譲受罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
Aさんは、大阪市鶴見区でリサイクルショップを経営していますが、数カ月前にお店で買い取った電動自転車のバッテリーが盗品だったらしく、大阪府鶴見警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、盗品と知らずにバッテリーを買い取っていたものの、この事を警察は信じてくれません。(フィクションです。)
盗品等の罪
人の物を盗むと窃盗罪(刑法第235条)となることは皆さんご存知かと思いますが、窃盗事件等で盗まれた盗品等をもらったり、買い取ったりすれば盗品等の罪で刑事罰を受ける可能性があります。
盗品等の罪は、刑法第256条に規定されており、その内容は以下のとおりです。
刑法第256条
1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の拘禁刑に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金に処する。
条文を解説する前提として、まず規制の対象となる盗品等についてですが、この法律でいうところの「盗品等」とは、窃盗や詐欺、横領、そして強盗や恐喝などの財産犯罪の被害品を意味しています。
そして盗品等の罪の主体となるのは、この財産犯罪を犯した犯人以外の者です。
この条文を解説すると、まず1項は、盗品等を無償で譲り受ける行為を規制している「盗品等無償譲受罪」が定められています。
盗品等無償譲受罪には罰金の罰則規定が定められていないのが特徴で、その法定刑は「3年以下の拘禁刑」です。
そして2項では、盗品等を運んだり、保管したりすることを規制した「盗品等運搬罪」や「盗品等保管罪」と、盗品等を買い取ることを規制した「盗品等有償譲受罪」について定められています。
今回の逮捕された男は、この盗品等有償譲受罪で逮捕されたようです。
2項で規定されている犯罪行為によって有罪が確定した場合の罰則は「10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金」と、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる非常に珍しい法定刑が定められているのが特徴です。
盗品と知らなかったら…
仮に盗品と知らずに、刑法第256条に規定されている行為をした場合はどうなるのでしょうか。
その場合は、刑事責任を負うことはないでしょう。
ただ、ここでいう「知らない」とは、『盗品だなんて想像もしていなかった。』というレベルでなければならず、少しでも「盗品かもしれないな・・・」という認識があれば、どこでどのような犯罪によって得られた盗品等であることまでの認識がなくても盗品等の犯罪が成立する可能性があるので注意が必要です。
まずは弁護士に相談を・・・
盗品等の罪は、故意、つまり盗品等の認識の有無が争点となることがよくありますので、盗品等の罪で警察の捜査を受けている方は、取調べを受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。
また既に逮捕されてしまった方へは、弁護士を派遣する初回接見サービスもご利用いただけますので、刑事事件に強い弁護士のご用命は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

制止しようとした相手を車で引きずり逮捕 岸和田市の殺人未遂事件
制止しようとする交通事故相手を車で引きずったとして、殺人未遂罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
Aさんは、車で大阪府岸和田市のドラッグストアに行った際、駐車場において、軽四自動車と接触する事故を起こしてしまいました。
運転免許証を自宅に忘れて不携帯だったAさんは、警察に通報されると厄介だと思い、そのまま逃走しようとしました。
ところが、軽四自動車の男性運転手が車から降りてきて、Aさんの車を制止しようと、Aさんの車にしがみついたのです。
Aさんは、しがみついた男性を振るい落とそうと、男性を引きずりながら数百メートル、車を走行させましたが、逃走することを諦めて車を停止させました。
そうしたところ、Aさんは通報で駆け付けた警察官に、殺人未遂罪で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
殺人未遂罪
上記事件のように、人がしがみついている車を走行させる行為は殺人未遂罪になりかねません。
そもそも殺人罪は、故意的に人を殺すことによって成立する犯罪で、相手が亡くなるまでの結果に至らなかった場合は殺人未遂罪となります。
ここでポイントとなるのが殺意(殺人の故意)の有無です。
ここでいう殺意とは、「殺してやろう」といった明確的なものでなくても、その行為によって相手が死んでしまうかもしれないと思いながらも、その行為を継続した場合にも認められます。
当然、殺意については人の内面に関するものであり客観的に分かるものではないため、行為者に殺意があったかどうかの真相は行為者本人にしか知りえないものですが、警察等は、その行為態様等によって、客観的に殺意を立証していきます。
つまり行為自体が、人を殺害してしまうほどの危険性が認められるならば、殺してしまう可能性を認識していたのだから、殺意もあるだろうというように考えられてしまうわけです。
制止しようとする交通事故相手を車で引きずると
以上のことを今回の事件に当てはめてみますと、車は立派な凶器であり、故意的に人に衝突したり、参考事件のように、車を走行させて車体にしがみついている人を引きずれば、相手が死亡する危険性が十分に考えられるので、殺人未遂罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。
逆に、運転手が、人が車体にしがみついていることを知らなかった場合は、車を運転するに当たっての注意が不足していたとして、相手が死傷すると過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)に問われる
でしょう。
逮捕された場合は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
大阪府岸和田市で刑事事件を起こして警察に逮捕されたなど、刑事事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。
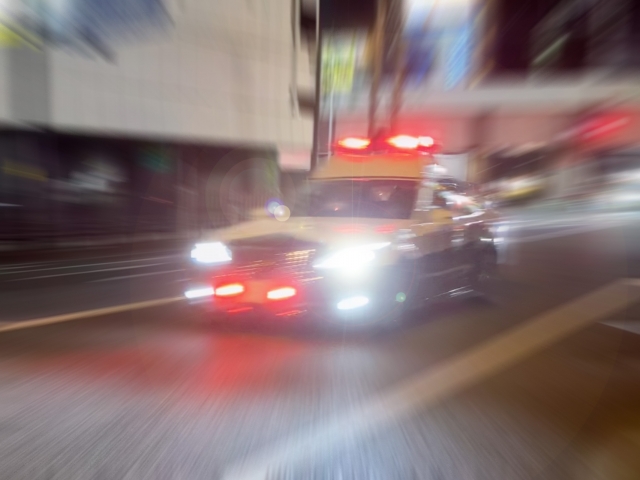
お店の売上金を横領 業務上横領罪で住之江警察署に逮捕
売上金を横領したとして、業務横領罪で店長が住之江警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
Aさんは、全国にチェーン展開する大手外食産業で店長をしていましたが、売り上げを本部に過少申告し、その差額を、売上金を保管している金庫から抜き取る手口で、横領を繰り返していました。
そして1ヶ月ほど前に横領行為が会社に知れてしまうことになり、その後の会社の調査で横領額は600万円にも及びことが発覚したのです。
すでに横領したお金を全て使い果たしていたAさんは、その後、住之江警察署に業務上横領罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
売上金を着服
自己の占有する他人の物を着服すると「横領罪」となります。
そして着服した物が、業務上占有していた場合は「業務上横領罪」となります。
刑法第252条1項(横領罪)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の拘禁刑に処する。
刑法第253条(業務上横領罪)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
今回の事件、元店長が横領したのは、お店で保管していたお店の売上金です。
まずお店の売上金は、店長の物ではなく、そのお店を管理運営する会社の物です。
そして店長は、その売上金を保管、管理する立場にあるでしょうから、元店長が着服した売上金は、業務上横領罪でいうところの「業務上自己の占有する他人の物」に当たるでしょう。
ですから元店長の行為が「業務上横領罪」に該当することは間違いないでしょう。
ちなみに、もし売上金を着服したのが店長ではなく、単なるアルバイトだった場合はどうでしょう。
おそらくアルバイト従業員に、お店の売上金を保管、管理する権限は与えられていないでしょうから、業務上横領罪ではなく、刑法第235条に規定されている「窃盗罪」が適用されるでしょう。
業務上横領罪の量刑
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑です。
業務上横領罪の法定刑には、罰金刑が規定されていないので、起訴されて有罪が確定した場合、執行猶予を得ることができなければ実刑判決となり、刑務所に服役しなければなりません。
実刑判決を免れるには・・・
業務上横領罪で起訴されて有罪が確定した場合、どういった刑事罰が科せられるかは、横領額と被害弁償の有無が大きく影響します。
横領額が100万円を超えて、被害弁償がない場合は初犯であっても執行猶予を獲得できる可能性が低くなると言われています。
ですから実刑判決を免れるためには、いかに被害弁償できるかにかかっています。
すぐに弁償できない場合でも、支払計画を立て、弁償を約束することによって、会社側と示談を締結できることもあるので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
業務上横領事件の弁護活動に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、業務上横領事件に関する法律相談を初回無料で受け付けております。
無料法律相談をご希望のお客様は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。

【少年事件】受け子で逮捕 逮捕後の流れは?
【少年事件】特殊詐欺事件の受け子で逮捕された少年の逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~ケース~
特殊詐欺の事件において、関東地方に住む大学生のAさん(18歳)は、他の共犯者らと共謀の上、現金の受け取り役(受け子)として大阪市城東区の被害者宅に赴き、被害者から現金500万円を詐取しようとしたところを、大阪府城東警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんは、本件以外にも同様の特殊詐欺事件に関与し、別の被害者2名から現金を詐取していました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、慌てて少年事件に精通する弁護士に接見依頼をしました。
(フィクションです)
少年事件の流れ
20歳未満の者(以下、「少年」といいます。)が刑罰法令に触れる行為を行った場合、捜査段階では、基本的に刑事訴訟法が適用されることになります。
ですので、少年であっても、成人の刑事事件と同様に、捜査段階で身体が拘束される可能性はあります。
ただし、少年が14歳未満の場合、刑事責任が問われませんので犯罪は成立せず、被疑者として逮捕されることはありません。
身体拘束が少年に与える影響の大きさから、少年の身体拘束については、成人とは異なる手続がとられます。
①検察官は、勾留に代わる観護措置をとることができます。(少年法43条1項)
②検察官は、やむを得ない場合でなければ、勾留を請求することができません。(少年法43条3項)
③勾留状は、やむを得ない場合でなければ発することができません。(少年法48条1項)
④少年鑑別所を勾留場所とすることができます。(少年法48条2項)
⑤少年を警察留置施設に勾留する場合であっても、少年を成人と分離して収容しなければなりません。(少年法49条3項)
少年事件については、捜査機関が捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると判断した場合、すべての事件を家庭裁判所に送致することとなっています。(少年法41、42条)
これを「全件送致主義」といいます。
少年事件では、成人の刑事事件のように起訴猶予に相当する処分はありません。
また、犯罪の嫌疑がなくとも、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがある場合には、「ぐ犯事件」として送致されることがあります。
家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官による調査、少年審判を経て最終的な処分が言い渡されます。
送致後、家庭裁判所はいつでも「観護措置」を決定することができます。
観護措置は、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置です。
この観護措置には、調査官の観護に付するものと、少年を少年鑑別所に収容するものとがありますが、前者はほとんど実務では活用されておらず、「観護措置」というときは後者を指すものとなっています。
調査官は、審判の前に、少年事件の調査を行います。
調査官は、少年や保護者と面会したり、学校や被害者に文書等で照会を行うなどして調査を行い、調査の結果とそれに基づく処遇意見をまとめた少年調査票を作成し、裁判官に提出します。
審判は、非公開で行われ、非行事実と要保護性について審理されます。
そして、審判において、裁判官は少年に対して処分を言い渡します。
特殊詐欺事件で逮捕された場合
特殊詐欺事件で逮捕された場合、逮捕後、勾留される可能性は高いでしょう。
また、特殊詐欺は組織犯罪であることが多く、共犯者と通じて罪証隠滅をおこなうおそれがあると認められ、勾留とともに接見禁止に付される可能性もあります。
特殊詐欺事件では、被疑者が本件のみならず他にも事件を起こしているケースも多いため、本件で逮捕・勾留された後に別件で再逮捕され、身体拘束期間が長期に渡ることも予想されます。
捜査段階で身体拘束となっている少年が家庭裁判所に送致されると、引き続き観護措置がとられることがほとんどです。
長期の身体拘束は、退学や解雇といった少年の大きな影響をもたらす結果を伴うおそれがあります。
勾留や観護措置に対する不服申立てを行うこともできますので、お子様が事件を起こして逮捕・勾留されてお困りであれば、刑事事件・少年事件に精通する弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

オンラインカジノで逮捕 常習賭博罪が適用
先日、オンラインカジノを利用したとして、常習賭博罪の疑いでテレビ関係者が逮捕された事件が報道されました。
1年ほど前からオンラインカジノが注目されて、これまで多くの芸能人やスポーツ選手等の著名人が警察に検挙されたり、検察庁に書類送検されて中には実際に刑事罰を受けた方もいます。
しかしこれまでオンラインカジノを利用したとして検挙された人たちに適用されていたのは、単純な賭博罪でしたし、警察に逮捕されたといった報道も聞いたことがありませんでした。
そこで本日のコラムでは、どうしてこのテレビ関係者が常習賭博罪で逮捕されたのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が検証します。
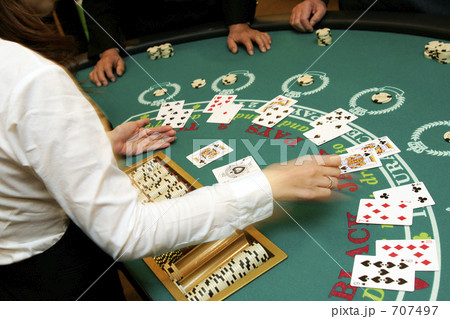
単純な賭博罪と常習賭博罪の違いは?
オンラインカジノを利用して賭け事をすれば刑法で規定されている賭博罪となります。
賭博罪には、単純な賭博罪(刑法第185条)だけでなく、常習賭博罪や賭博場開帳等図利罪(刑法第186条)があります。
単純な賭博罪と常習賭博罪の大きな違いは法定刑です。
単純な賭博罪は、50万円以下の罰金又は科料と、有罪になったとして科せられる刑罰は財産刑のみで刑務所に収容されることはありません。
しかし常習賭博罪は、3年以下の拘禁刑と、単純な賭博罪とは逆で、罰金等の財産刑の規定がないので、起訴される刑事裁判で裁かれることとなり、そこで有罪が確定すると執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。
警察に逮捕されるの?
単純な賭博罪については法定刑こそ軽いものですが、罰金刑の上限が50万円ですので警察に逮捕されないとは限りません。
ただ常習賭博罪と比べると逮捕されるリスクは低いでしょうし、逮捕されたとしても事実を認め、証拠がハッキリとしている場合は比較的早い段階で釈放されると思われます。
常習賭博罪となるケースは?
捜査当局が常習賭博罪で立件するには、常習性を裏付ける必要があります。
常習性の裏付けには、賭博行為をした回数だけでなく、賭けた金額や、賭け事の内容、そして賭博罪の前科前歴の有無などが考慮されます。
今回の事件で逮捕されたテレビ関係者は、テレビ局の社内調査が行われた後も賭博行為を続けており、さらに賭けた金額も1億円にのぼると報道されていることを考えると、常習性が裏付けられての逮捕となったのではないでしょうか。
(参考記事はこちら)
賭博罪で摘発されると
今後もオンラインカジノを利用しての賭博行為に対する摘発が続くことが予想されます。
ある日急に警察から呼び出しがあったり、急に逮捕されることもあるかもしれません。
オンラインカジノを利用して賭博行為をしてしまった過去がある方は、早めに弁護士に相談しておくことをお勧めします。
ネット通販を装い代金詐取 詐欺罪で逮捕
大阪府大阪市西区で、通販サイトを装い商品代金を騙し取ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪府大阪市西区に住むAさんは、人気のゲーム機やブランド品を定価より安く販売しているかのように装う、架空の通販サイトを開設しました。
サイトには実在する企業のロゴや写真を転載し、あたかも正規の販売店であるかのように見せかけており、購入希望者からは銀行振込で代金を受け取っていました。
被害者であるVさんは、SNS広告を通じてそのサイトにアクセスし、約8万円のゲーム機を注文して代金を振り込みましたが、商品は届かず、連絡も取れなくなりました。
不審に思ったVさんが大阪府西警察署に相談したことで捜査が開始され、サーバーのアクセスログや振込口座の名義などから、Aさんがサイトの運営者であることが特定されました。
その後、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
詐欺罪
詐欺罪とは
詐欺罪は刑法第246条に規定されており、条文は以下の通りです。
第二百四十六条(詐欺)
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は、大まかに言えば、人を欺いて財物を交付させ、不法に利益を得る犯罪です。
2項は、詐欺利得罪という罪を規定しており、2項詐欺などと言われています。
詐欺罪が成立するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
①欺罔行為(欺く行為)
欺罔行為とは、相手方が真実を知っていれば財産的処分行為を行わないような重要な事実を偽ることをいうとされています。
詐欺罪において最も重要な要素は、この「欺く行為」と言ってよいでしょう。
Aさんの場合、架空の通販サイトを解説し、あたかも正規の販売店であるかの装ったことがこれに該当します。
②錯誤
詐欺罪における錯誤とは、財産的処分行為をするように動機付けするものであれば足りるとされています。
今回の事例では、Vさんは、Aさんのサイトからゲーム機を購入できると思い、実際に注文していることから、Vさんが錯誤に陥っていたと認められる可能性が高いと言えます。
③交付行為
詐欺罪の成立には、交付行為が必要です。
今回の事例では、Vさんは代金を振り込んでおり、これが交付行為に当たります。
④財産上の損害
詐欺罪の成立には、財産的損害の発生も必要となります。
詐欺罪も財産犯である以上、実質的な財産的損害が必要であり、被害者の意図した交換の失敗が必要であるとされています。
今回の事例では、Vさんはゲーム機を受け取れると思い代金を振り込んだにもかかわらず、商品が届かなかったため、意図した交換の失敗があり、財産的損害が発生したと言えるでしょう。
弁護士に相談するメリットと事務所のご案内
早めに弁護士を付けることで、早期に示談交渉を開始することができる・早期保釈の可能性が高まるなど様々なメリットがあります。
相談を受けたタイミングが早ければ、それだけ時間的な余裕が生まれ、より充実した弁護活動を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
詐欺事件を含め、幅広い刑事事件の対応実績があります。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談ご予約・初回接見のご依頼を受け付けています。
フリーダイヤル:0120-631-881
詐欺事件その他刑事事件・少年事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。